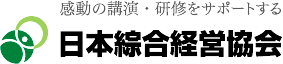2016年10月 福岡政行先生の講演を聴いてきました2017/01/17

10月に都内ホテルで、弊社お客様ご主催で、福岡政行(ふくおかまさゆき)先生の「今後の政治と経済の動きをよむ」と題しての講演を聴いてきました。
前日九州で羽田空港からご自宅経由で会場入りされ、講演終了後は翌朝の授業の為仙台入りされるという多忙な中にもかかわらず懇親会にもご出席頂きました。
会場のホテルは学生時代の思い出がたくさん詰まった懐かしい所だという話を控室でされ、主催者の皆さんとも和気あいあいと談笑、そして記念撮影とにこやかにご対応下さいました。
また、大昔の話ですが私の友人2人の家庭教師が福岡先生だったこともあり、妙に親近感が湧きその話で盛り上がりました。
講演の方はまず北方領土、小池百合子都知事、天皇陛下の生前退位の話。
引き続き米国大統領選、アベノミクス、デフレ、蓮舫氏、松下政経塾のこと。
さらに安倍総理後の候補について。
その中の一人、小泉進次郎氏と東北の仮設住宅の集会所で会った時のエピソード。
手土産も持たず、出してもらったお茶を飲み、おばあちゃんからおやつを貰って食べて一礼して帰る。
他の議員はこれ見よがしにたくさん手土産持って渡すところを秘書が写真撮影し、わずか10分の滞在、翌日にはホームページにUPして宣伝するが彼は一切しない。
そこが良い所。
他党の政治家の話、米国、ロシア、中国等との外交について。
安倍総理にはブレーンがいない。
田中角栄氏には“鉈”の金丸信氏、“剃刀後藤田”と言われた後藤田正晴氏という懐刀がいて意見を聞いた。
2025年問題。
団塊シルバーが後期高齢者になる約10年後。
長生きはして欲しいが「長寿」は「長苦」という感覚に持って行かなければならないかもしれない。
約10年後に消費税は20%まで行くだろう。
竹下登氏が総理の時に「消費税が10%になった時に軽減税率を導入することになっている」と言われ、政治とはそういうものなのだと思った。
東京と名古屋圏以外は人口も減少しやっていけなくなるだろう。
人口減が進む以上、5万人以下の市町村の合併を進め、効率的に運営するしかない。
AI(人工知能)、IoT、ICTを活用し、省力、省人化しなければならない。
つい先日も「地方の金融機関は無くなる」という記事が複数同時に出た。
今の政治家には未来志向がない。
ユニクロの柳井正氏が「NEXT ONE」、「NEXT SOMETHING」ですと言っていた。
10数年前、城山三郎先生が講演の中で「時代を生き抜いてきた人間は高感度のアンテナで時代の周波数を見極めている」と話されていた。
福岡先生は現在、名前だけで何もしない名誉教授“である”ことよりも、学生に教える(“する”)ことを選択され、結果を出せるリーダー育成に取り組まれておられる。
結論、「“である”価値より“する”価値」と結ばれた。
講演では実名を出され過激に聞こえてしまうことを言われるので、詳細は書けませんでしたがご容赦頂けますと幸いです。
著名人、著名企業、役人など政治、経済関係に留まらず友人・知人・後輩・教え子・お弟子さんが多岐に渡り重要な地位を占める多数の人脈を持ち、ボランティアにも注力され、空手三段で、「可愛くて仕方がない」9・6・3歳のお孫さんたちの良き“ジイジ”の福岡先生でした。
2016年9月 伊藤元重先生の講演を聴いてきました2016/12/27

都内で、長年の弊社お客様ご主催で、伊藤元重(いとうもとしげ)先生の「日本経済と不動産業」と題しての講演を聴いてきました。
まずはわかり易く日経平均、株、マイナス金利、日銀、国債などの解説や見通しに加えて聴衆が不動産関係の方々であることからJ-REITについても。
量的緩和を減らしマイナス金利をもう少しやるのではないか。
経済の浮上を待つために超低金利は当分続くだろう。
不動産業界においては伸びるものとそうでないものとが顕著になるだろう。
成長戦略で最も大事なことはグローバル化。
改造したばかりの内閣での注目の大臣について。
OECD、先進国35か国の中で、日本の女性が最も睡眠時間が短い。
ドイツは日本より労働時間が2割少なく働き、5割も労働生産性が高い。
これからの日本はワークライフバランスを進め、女性とシニアに働いてもらい、欧米の男性の半分しか家事をやらない日本の男は、もっと家事をしなければならない。
今後、企業の最大のポイントは「人」(の確保)。
毎年1%ずつ労働人口は減っていく。
つまり目安として年3%昇給ができないと人の確保は難しいということ。
付加価値労働生産性を上げない企業は生き残れないだろう。
最後に世の中を一番変える動きについて。
これはAI(人工知能)、IoT、ビッグデータなどなど。
凄まじい勢いで変わっていく。
一例だが、情報が「金融」を変えてしまう。
世界最大の銀行、JPモルガンがインタビューにこう答えている。
5年後の最大のライバルはゴールドマンサックスや三井住友などの既存金融機関ではなく、グーグルだ、と。
そしてアップルだ、とも。
フィンテックにより金融が大きく変わっていく。
金融機関以外が顧客の信用情報に基づき独自にお金を貸すようになる。
その他にもものづくりや医療なども情報化の進化により変わる。
最先端の情報をアルファ碁の話や10年後にはスマホに日本語で話し掛けると英語になるといった「完璧な翻訳機」が出現するといった話を交え、わかり易く興味を持ってもらえるように、これから来るであろう近未来の様子が目に浮かぶ内容で、さすがにあらゆる分野に精通され、飽きる事の無い90分でした。
不動産業界に特化した内容も織り込んで頂き主催者の方々にも大変喜んで頂けました。
2016年9月 朝原宣治先生の講演を聴いてきました2016/12/06

9月2日に都内で、弊社お得意様ご主催で、朝原宣治(あさはらのぶはる)先生の「夢を追いかけて ~諦めなければ夢は叶う~」と題しての講演を聴いてきました。
リオ五輪の余韻タップリのタイムリーなタイミングで、正にベストチョイスの講師でした。
控室で朝原先生とお話しする中で、「今100mをどのくらいのタイムで走れますか?」と訊ねましたら「12秒台でしょう。ただ一週間トレーニングすれば11秒台、6か月トレーニングすれば10秒台は出せます」と自信満々に答えられ驚きました。
朝原先生は既に44歳ですから。
ただ最後に笑顔で「6か月もトレーニングできませんけどね」と言われたので少し安心しました。
さて講演の方は、まずリオのリレーの話から。
リオの400mリレーチームが銀メダルを獲得。
北京の時は先輩たちの思いや技術や経験を引き継いで、ここ(銅メダル)まで我々は来たということを、本音でメンバー皆が言っていた。
リオにもバトンを繋ぐために様々なことが引き継がれてきている。
リレーはタイムが速い者だけ集めれば良いというものではない。
第一走者からアンカーまでそれぞれ特徴があり、それを上手く活かせたら良いパフォーマンスに繋がる。
北京とリオでのそれぞれのメンバーの役割と特徴の解説。
今年のリレーメンバーはサブがとても充実していた。
怪我をしたり調子が悪いと代えられるかもしれないという危機感をメンバー同士が持ち、良い緊張感の中でオリンピックを迎えられた。
現在のリレーチームはもの凄い良いチームになりつつあり、若手もどんどん育ってきており2020年の東京が楽しみ。
もしかしたら金メダルが現実になるかもしれないくらい。
「バトンパスについてはリオ五輪期間中にTVで100回くらい説明したので割愛します」とウケを取られ、日本チームのバトンパスの何が凄かったかを具体的に解説。
また、自身のロンドンの時との違いも。
リレーでのバトンは1走は右手、2走は左手、3走は右手、4走は左手に持ったままというのが主流。
アンカーのウサイン・ボルト選手だけはバトンを持ち替える。
その方が走り易いかららしいが、本来はタイムロスに繋がる無駄な動き。
アメリカチームはバトンパスが超下手。
北京五輪の時にはバトンを落とし失格に。
何とこの時のアメリカチーム(男女ともに)のゼッケンが手書き。
オリンピックではあり得ないこと。
帰国後、日本のリレーチームが外国人記者クラブに招かれた時、この4人で東京オリンピックに出場する確率を訊かれ「40%」と答えていた。
4年後に皆いるのかと思うと、そんなもんだと思う。
選考会で選ばれた者だけ、つまり結果を出さなければならない。
怪我もある。
ピークも過ぎるかもしれない。
ロンドン以降様々なデータがリレーにおいても取られ、選手同士の感覚の擦り合わせからデータ(数字や映像)活用へと変わってきている。
桐生選手が10.10秒で走った時、追い風2.0m、60m付近で最高速11.51m/秒。
どんな選手も最高速から落ちながらゴールする。
9秒台を出すには計算上最高速11.7m/秒以上が必要と言われている。
ウサイン・ボルト選手は70m付近で最高速12.4m/秒、ほぼそのままの毎秒12mオーバーでゴールする。
桁外れ。
朝原先生は中学時代ハンドボールの選手。
この時にセルフマネージメントでは到底できない練習でメンタルな部分含めて成長できたが、燃え尽き症候群でハンドボールの「ハ」の字を聞くのも嫌なぐらい大嫌いになり、高校で陸上を始めた。
徐々に力を付けていきインカレで優勝できればとは思ったが、オリンピックまでは全く考えていなかった。
夢のまた夢だったが、当時知り合った奥野史子氏(現在の奥様)は既に大学時代には世界レベルで、2年生の時にバルセロナ五輪代表に選出された。
お付き合いしていたので、「一緒にオリンピックに行こう」と言われ、行けないんじゃないかと思いつつ「よし、絶対に行こう」と答えたが、内心「ちょっと、これ、オリンピックなんて・・・」と思っていたら予想通り彼女だけ出場。
結果彼女は銅メダルを2つも獲った。
そして帰国後はデートもままならないほど彼女のスケジュールが取れなくなり、親戚が増え、大変なことになり衝撃だった。
オリンピックでメダルを獲ることは凄いことなんだと。
オリンピックに出たい、そして今しかできないことに覚悟を決めて取り組もうと全力投球した。
彼女はそのキッカケになった。
大阪ガスに就職でき、プロ第一号のように扱ってくれたおかげで、ドイツ留学もさせてもらった。
1999年に左足くるぶしを疲労骨折という挫折も味わったが、およそ1年後のシドニー五輪に出場できた。
その後渡米し、自分よりもはるか上の選手たちとも一緒に練習。
その中で敵わないと思う反面、もしかしたらできるかもという感触や戦う方法も得られた環境だった。
そしてアテネ五輪、大阪の世界陸上。
大阪の世界陸上では大阪ガスの社員2000人の大応援団。
家族や会社など背負うべきものがあったことが人間的にも成長できた要因のひとつ。
そして36歳で迎えた自身最後の北京五輪で素晴らしいリレーメンバーと巡り合え、結果を残せたことはとても幸運なことだと思っている。
リレーは決勝に常連のように残りメダルを獲れるようになってきた。
100mはまだ決勝に進んだことはないが、リオでは山縣選手は決勝まであと40cm、100分の4秒の所まで来た。
何をし、どう戦うか。
2020年の東京オリンピックがとても楽しみ。
自分自身が日本の為に何ができるのかを考えながら。
さすがにメダリスト。
説得力はハンパありません。
やってやれないことはないと思わせてくれる前向きになれる内容です。
陸上ファンには堪らない。
そうでない方もマネジメントやモチベーションで多々参考になります。
また、高校生以下の若い人や子供たちには得るものが大きな内容ですし、「走り方教室」的なものもやっておられます。
実際に走りを見せることもあるようです。
2016年8月 田中雅美先生の講演を聴いてきました2016/11/22

8月24日に都内で長きにわたる弊社お得意様ご主催で、田中雅美(たなかまさみ)先生の「オリンピックと私 ~競技人生で培われた人間力~」と題しての講演を聴いてきました。
リオ五輪後初の講演だったそうです。
映像(DVD)で引退までと引退後~現在の講師紹介で講演スタート。
最初のオリンピックが17歳で出場した1996年アトランタ、2度目が2000年シドニー、3度目がアテネに出場し、現役引退。
今回のリオの金メダル第一号が萩野公介選手。
事前の解説で萩野選手か瀬戸選手が金メダルを獲る確率100%と公言。
普段から二人を見続けてきたからこそ、勇気は要ったが言えたことだったということが、分析を聞いて良く分かった。
松田丈志選手が出場し見事銅メダルを獲得した自由形800mリレーの秘話。
萩野選手の凄さ、泡が立たない手の入水の仕方、「足を入れる」とは?など様々な話をわかり易く。
田中雅美先生の17歳で初めてのアトランタ五輪での成績は、200m平泳ぎに出場し、自己ベストを出して5位だった。
オリンピックでメダルを獲るには80%の力で戦える力が無いとそこでは戦えないと言われてきた。
体操の白井健三選手は戦前予想で床の金メダルの確率200%と言われていたが、結果は4位。
普通にできていれば誰も追い付けないほどの実力を持っていてもメダルが獲れなかった。
それほど難しい。
オリンピックの水泳会場には2万人の観客、その歓声がどのように選手に伝わるかというと、音がブルブルと振動となって伝わり、ピリピリ、ジリジリ感じる。
独特の雰囲気、空気感の中で戦う難しさ、厳しさ。
自己ベストを出してもメダルに届かないということは、もっと努力し戦える気力、実力を付けなければいけないと思った。
そして改めてメダルを目指し、臨んだ2000年シドニーオリンピック。
非常に苦しい、辛い大会だった。
代表選考レースで、予選、準決勝、決勝と全て日本記録を更新し、決勝のタイムは当時歴代2位のタイムでメダル確実と言われた。
すると環境は一変し、思うように体が動かず、練習ができない状態に。
更には「努力は無意味」「水泳なんて楽しくない」と思うほどだった。
その結果個人種目は100m6位、200m7位。
そして最後はメドレーリレー。
戦前予想は持ちタイムから日本かドイツのどちらかが3位に入るだろうというものだった。
リレー直前に大西順子先輩から掛けて貰った言葉。
「この4人なら絶対にメダル獲れるから、雅美は自信持って泳ぎなさい」と。
「努力は無意味」「水泳なんて楽しくない」と思っていたのが嘘のように「このメンバーだったらやれる」と心底思えた。
このレースの模様と表彰式をノーカット映像で。
0.3秒差でドイツに勝ち、銅メダル。
仲間のお蔭で獲ることができた銅メダル、感謝の思いで一杯。
リオのメダルはもの凄く大きくて重たいと選手たちが言っていたが、規定上限の500gもあった。
田中先生にとってはとても重かったが、シドニーのメダルは半分以下の230gしかない。
聴衆の皆さんに実際に持って触って首に掛けてオリンピックを少しでも感じて頂きたいと実物の銅メダルを持参、会場内を回しすべての方に手に取って頂いた。
中には首に掛け写真を撮りあう方も。
コーチ、両親、トレーナー、チームメイト、応援して下さった全ての方々に支えられた結果が銅メダル。
陸上リレーのバトンパスが重要なことと同じで、水泳も“バトン”(タッチ)が大切。
全チーム中、合計タイムが1位(一番少ないタイム)だった。
帰国し多くの方々から「おめでとう」「頑張ったね」などと声を掛けて頂き、手紙を頂いたりした。
また、リレーメンバーだった中村真衣さんとディズニーランドに行った時、ミッキーマウスと写真を撮ろうと思ったら、ミッキーが泳ぐ格好をしてくれ、「覚えてくれていたんだ」ととても嬉しかった。
シドニーでは個人でのメダルは獲れず悔しい思いをした。
水泳を辞めようと思ったが、もう一度自分が頑張ったと思いたいという気持ちと応援して下さった方々へ恩返しをしたいとの思いから、もう一回アテネへ行きたいと思った。
練習がきつすぎてゴーグルに自分の涙が溜まるほど。
でもそのきつさよりも辛いことがある。
モチベーションを保ち続けるといったメンタルの部分。
自分を信じ続けることは凄く大変。
リオでも金藤選手が何度も辞めようと思ったが、続けてこられたのは加藤コーチのお蔭だと言っていた。
加藤コーチは「お前は絶対にやれる」と言い続けてくれた。
自分自身が自分に自信を持てなくなる時があり、何度も挫折してきたことで、オリンピックにもう行けないのでは、メダルも獲れないのではないかと思う自分を信じ続けてプールに向かう大変さ。
そういう時に支えになってくれる周りの人の大切さ。
二つの言葉。
一つ目はアテネの1年前にもうダメだと思い水泳を辞めたいと掛けた電話で母に泣きながら言われた言葉。
「親としては一生懸命やったねと言ってあげたいけど、アテネまでやると自分で決めたことは最後まで諦めずに続けなさい」と電話を切られた。
要は自分で決めたことは諦めてはいけないのだ、ということ。
二つ目はアメリカでトレーニングをし、タイムに一喜一憂していた時に出会ったコーチの言葉。
「次の大会のレースが終わった後タイム(電光掲示板)を見るな。まず自分の心に聞け、100%でトライできたか?できたと思ってから見ろ。」
調子は日々変わるが、一番大事なことは毎日の練習で自分が100%トライできたかということで、タイムが速い遅いではないということを言わんとしていたのだと気付かされた。
この100%を日々重ねることなのだと。
こうして迎えたアテネ。
100mは準決勝敗退。
200mは4位。
3位の選手との差は0.05秒。
距離にして約2cm。
小さいけれど大きな差。
たったこれだけの差でメダリストになれなかった。
帰国してまた厳しい現実。
成田空港でメダリストとそれ以外で分けられ、メダリストだけ記者会見場へ。
引退して12年、メダルコンプレックスが確かにある。
でも、あれをすれば獲れたのにということが無い。
スタート台に立った時にやり残したことが一つも思い浮かばなかった。
悔しいし欲しかったし獲りたかったと思うけれど、後悔していない。
そう思った時に、泳ぎ切ったなと引退をすんなり受け入れることができた。
何て素晴らしい水泳人生だったと思う。
個人のメダルは叶わなかったが、人生においてとても大切な多くのものを得られたり、学ばせてもらったと思っている。
子供たちに伝えてあげるとしたら、自分の夢や目標は自分自身で決めて欲しい。
そして自分で決めたことは、自分に負けずに挑戦し続けて欲しい、と。
メダルの色ではなく、選手がオリンピックという舞台で自分の力を出し切ることが一番大事で、その為のサポートや応援ということなのではないかと思う。
リオ五輪の総括をされ、テレビ朝日「グッドモーニング」水曜日レギュラーなので是非ご覧下さいという告知も忘れずにされた。
最後に質問を受けられ、丁寧にわかり易く答えられ、スイマーでなければ知らないであろう水泳トリビアも入れて下さり興味深く楽しく聴くことができました。
一生懸命さが伝わるアスリートらしい爽快感が余韻として残る大変良い講演で、田中先生はとても礼儀正しく、爽やかでチャーミングで素敵な大人のレディでした。
2016年10月 谷田昭吾先生の講演を聴いてきました2016/11/08
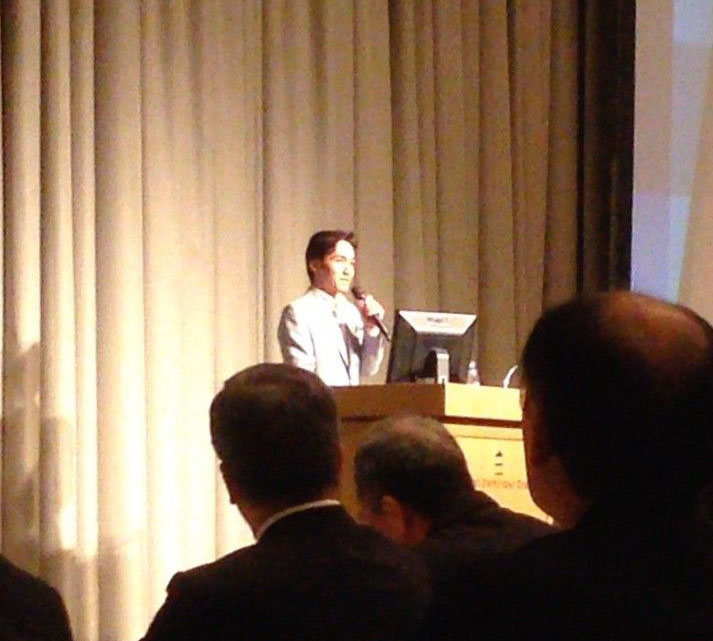
先日、都内ホテルにて人気講師・谷田昭吾(たにだしょうご)先生のご講演を拝聴してきました!
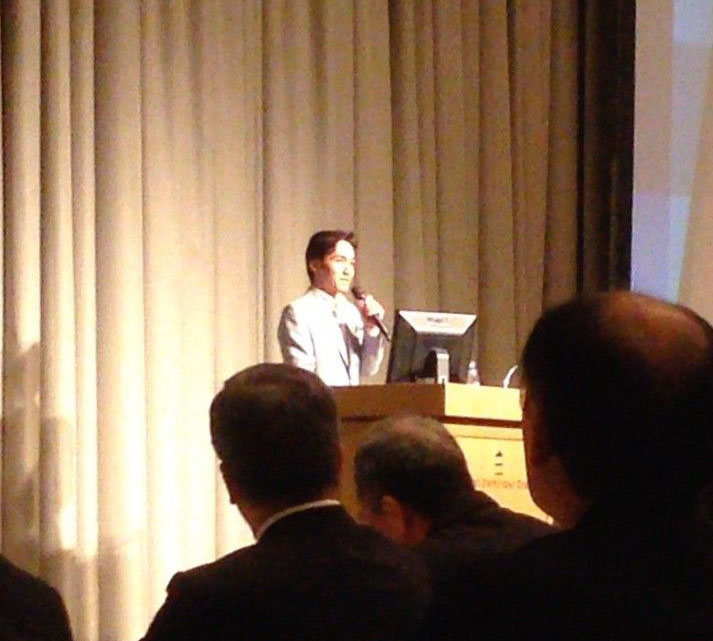
スマホの無音カメラで撮影させていただいたため、画質が荒く申し訳ありません…😢💧
ご講演前には控室でお話もさせていただきました。
とにかく物腰柔らかなお人柄!😍😍
ご講演日前の打合せ段階でも、常にお気遣いをいただき
またよりよいお話をめざしておられる方だとは感じていましたが、
この日も控室にて、「もっと良い講演にしていきたいと思っています」とお話くださり、
強い向上心を持っておられる先生なのだなあと改めて思いました。
今回のタイトルは「タニタの成功法則 ~タニタを世界No.1へ導いた“経営の秘訣”とは~」。
詳細な内容は以前弊社代表が拝聴した際のレポートをご覧いただければと思います。
(同じタイトルでのご講演の際のレポートです)
とくに有名な「タニタの社員食堂」誕生に至るまでのお話は感動的!
強く印象に残るエピソードでした。
配布資料には心理学的なエクササイズ方法や、自分の考え方を見直すためのワークシートも。
経営者層のお客さまには、きっと皆様それぞれのお仕事に役立つエッセンスを
お持ち帰りいただけたと思います👩🌟
ご講演後にお礼を申し上げると、
「今回も改善点や可能性を見つけることができました」とおっしゃっていました。
研鑽を重ね、今以上にパワーアップしたご講演もぜひ聴いてみたいです❣
谷田先生、主催者のみなさま、どうもありがとうございました!
(文・スタッフW)
2016年9月 弘兼憲史先生の講演を聴いてきました2016/11/08

9月29日に名古屋で弊社長年のお客様ご主催で、弘兼憲史(ひろかねけんし)先生の「島耕作から見る日本の未来像」と題しての70分講演を聴いてきました。
「島耕作」の連載を始めて33年目。
笑顔で広島東洋カープファンを公言され、相撲のことなどざっくばらんに話され、会場も笑いに包まれてのスタート。
高齢化社会の話をされるつもりで準備してこられたが、新幹線の社内誌「Wedge」に尖閣のことが掲載されていて、急遽内容を変更。
2012年に島耕作で中国が尖閣を手に入れようとしたらどういう手段を取って来るか、そして魚釣島に上陸したらというシミュレーションなどを詳細に描いたら、正にその通りになり編集者と一緒に小さくガッツポーズ。
半端ない取材力、正確さに脱帽です。
リアルに細かい描写で想像できる光景を言葉で表現。
さすがです。
また、日本は一国平和主義では絶対にいけない、その為には「集団的自衛権」が必要と言いたかったから「加治隆介の議」を描き始めたが、1992年当時は知られていなかった。
「集団的自衛権」と「集団安全保障」とは全くの別物だが、区別がつかなかった時代だった。
「集団的自衛権」と「集団安全保障」の違いも分かりやすく解説。
日本は戦後戦争に巻き込まれなかったのは、憲法9条があったからと日本人は思い込みをしているようだが、日本以外にも同じような憲法を持っている国々があちこちにあるのに、なぜ日本は平和でこられたのか?
間違いなく日米安保条約があったからだと言わざるを得ない。
だから他国から侵略されなかったのは紛れもない事実。
中国からそうされなかったのもそう。
アメリカのプレゼンスが無くなればどうなるかはフィリピンを見れば明らか。
ソフトパワー(話し合い)で解決できることは大賛成だしベストだと思うし、そういう時代が来ることを切に望むが現状は無理。
日本が今考え、今やるべきこと、これからすべきことを、例え話も交えはっきりと示された。
最後の10分余りでご用意してこられた高齢化社会の話をされた。
多くの資料、詳細なデータとその分析に基づき、現状を把握し、未来を予測し、今何をして将来に備え、先々の変化にどのように対応しなければならないかなど、講演内容全てに通じる弘兼先生のポリシーが滲み出ている有意義な講演でした。
大変失礼ながら、とても69歳には見えない若々しく素敵な弘兼先生。
柔らかな外見とは裏腹に硬派な面もお持ちで、主義主張がはっきりしておられ、古臭い言い方ですが、気骨ある日本男児という印象を強く受けました。
講演は多くても年に数本が限度。
それも伝手が原則。
さらに今回のように東京を離れることは至難。
従いまして当然弊社のHPで大っぴらに講師としてご案内はできませんし、どうしても弘兼先生でなければと仰って下さるご主催以外はお断りさせて頂いておりますのが現状です。
今回の講演につきましては特別に弊社HPへの掲載をご快諾下さいました。
2016年6月 山本昌邦先生の講演を聴いてきました2016/10/25

都内で弊社お客様ご主催の講演会で山本昌邦(やまもとまさくに)先生の「リーダーの条件 ~一流選手から学ぶ目標達成へのプロセス~」と題しての講演を聴いてきました。
前半は一流選手たちがどんな特徴を持ち、どのように成長していったか、を。
“ハーフタイム”ではワールドカップなどの映像を。
後半は一流選手たちをどう纏め、どのように使い、難しい局面を打破し、勝利に導いたかというマネージメントについて。
ワールドカップからクイズ形式で出題。(おそらく聴衆との一体感の演出のひとつと思われます)
トリビア的知識も。
パスが一番下手なチームがイングランドプレミアリーグでなぜ優勝できたか?という岡崎慎司選手所属のレスターの話題も。
インテル・ミラノの長友佑都選手は中学まで愛媛で、高校は東福岡、早くプロになりたかったがどこからも声が掛からず、仕方なく大学へ進学。
そこでもサッカーをさせてもらえず、スタンドで応援の日々。
これではダメだと練習に没頭し、在学中にFC東京へ入団し、現在がある。
ACミランの本田圭佑選手はガンバ大阪の中学のジュニアユースに在籍していたが、プロでは通用しないと言われ、高校のジュニアユースには入れてもらえなかったので仕方なく星稜高校へ行き雪塗れになり一生懸命練習し、高校選手権でそこそこ活躍したので、名古屋グランパスから声が掛かり今がある。
15歳で大きな挫折を味わい、悔し涙を流したと思う。
横浜マリノスの中村俊輔選手は横浜マリノスの中学のジュニアユースに在籍していたが本田選手同様高校のジュニアユースには上がれず、仕方なく桐光学園高校に進学し、高校選手権で準優勝。
U20の代表監督だった時に代表に呼び、今も当然付き合いがある。
彼らの周りには高校のユースに上がった連中が山のようにいたが、皆どこへ行ったのか?
「努力する才能」が無い人は残念ながら無理。
一流選手に共通する特徴、「負けず嫌い」「自分の意思でやる」「人の話が聞ける」「高い目標を持っている」こと。
つまり自分の考えることや持ってる能力程度で、言われたことだけを一生懸命やって世界のトップレベルに行けるほど簡単な世界ではない。
折れても折れても立ち上がって来る本田選手のような良い習慣を若い時に身に付けた人が強い。
サッカーが上手いだけでは通用しない。
リーダーは目に見えない意欲や情熱(といったメンタルな部分)が見えるようにならないと務まらない。
Jリーグで2回得点王にもなった中山雅史氏。
ギネス記録も2つ持っている。
1つは「試合開始5分未満で4点取った」というもの。
2つめは「4試合連続ハットトリック」という記録。
サッカーは超下手、見せられる技術は何もないのでサッカー教室には呼べない。
実はサッカーのゴールの7割はワンタッチシュート。
ワールドカップ ブラジル大会では全ゴール171点の内92点がペナルティエリア内でのワンタッチシュート。
いかにマークを外しそれができるかが肝心。
中山選手は技術は無いがマークを外せば独壇場。
「技術・戦術・体力」の中の「技術」は100点満点で20点だが、彼は努力の天才。
初めて出場したフランスのワールドカップで日本の歴史的初ゴールも中山選手。
この時彼の足は骨折していたが、「まだできます」と言ってやった選手。
彼は止めさせないと死ぬまでプレーする選手。
精神的限界と肉体的限界がほぼイコールまでできる選手。
メンタリティは人の10倍くらいある。
サッカー選手には特に大事。
人を育てない限り勝利に近道は無い。
少なくとも10年後を見据え、人を育てないと勝てるチームは作れない。
2002年ワールドカップ直前、スペインでの合宿中、30人から23人に絞る段階で選手たちに戦う魂が無い、誰か持ってる選手はいないのか?とトルシエ監督から言われ、当時コーチだった山本先生は「います、中山(雅史)、秋田(豊)が」と答え、中山選手に電話。
山本先生「もしもし、ゴンちゃん」
中山選手「山本さん、俺電話待ってましたよ」
山本先生「(まだ諦めてないのかよ、1年半も代表に呼ばれてないのにと思いつつ)調子はどうだ?」
中山選手「僕ですか、常に絶好調に決まってるじゃないですか」
山本先生「実はこうこうでこうなってる。力を貸してくれるか?」
中山選手「もちろん行きますよ」
山本先生「試合で結果出せよ」
そして結果を出し、両名が招集された。
そして迎えた埼玉スタジアムでのワールドカップ初戦を勝利した。
年齢的な衰えで1年以上候補からも外れていた、パフォーマンスから言えば22番目と23番目の選手が、チームの勝利の為に、監督コーチに何も言われずとも自分で考え、とてつもなく高いモチベーションで、若い選手を支え、相談に乗り、叱咤激励し、チームの中(現場)のリーダーの役割を担ってくれた。
永年選手たちに言い続けてきたこと。
勝つことが大切ではない。
諦めないことが大切なんだ。
自分がしたことに絶対に満足しないことが大切なんだ。
気を抜かないことが大切なんだ。
自分に期待してくれている人をがっかりさせないことが大切なんだ。
もちろん勝つためにプレーするが、負けた時にはチャンピオンが負けた時のように堂々としていればいい。
相手がズルいことをしたとか、審判が間違えたとか、ピッチが良くなかったからとか、風が吹いたとか、監督がアホだからとか言い訳せず、自分に何が足りなかったか、勝利する為には何ができたのだろうか?を考え、次にぶつける。
これがスポーツの良い所。
またチャレンジするチャンスがあるということ。
スポーツは教育的なこと、例えば挫折、みじめさ、苦しさ、達成感、喜びなどほとんど全てを学べる。
負けて諦める人には何もない。
負けても諦めないことが勝利の始まり、希望の始まり。
どんなに才能があっても諦めたら終わり。
大切なのは勝つことではなく、挑戦し続けること。
リーダーに必要なもの。
①個性を生かすこと。
②当然専門知識を持っていること。
③指導能力、説明が上手いことではなく説得できること。
③が最も大事。
本人が納得し、自分の意思でやれば大抵の目標は達成できる。
伝えたつもりが伝わってなければ意味は無い。
だから「伝わり」にこだわる。
感情に結び付かないマネージメントは絵に描いた餅。
やるのは人間。
試合前のマネージメント。
ストレスやプレッシャーからどうプレーヤーを守れるか、助けられるかを一番に、ポジティブな指標を与え、自分自身のパフォーマンスとチームへの貢献を考えさせ、むやみに結果のことを言わず、その人が長所、得意なことを認識して自信が持てるように配慮する。
話し掛ける際の主語、「君たち」と「我々」の使い方の具体例。
先発とサブが一体感を生み出すミーティングの手法。
ハーフタイムですべきこと。
偉大なリーダーは選手たちの感情を揺さぶり、情熱に火を付け、秘められた資質を呼び覚ます。
カリスマリーダーは共感を呼ぶ力を持っている。
レスターのように選手たちの良い所を最大限に引き出せる監督が良い監督。
私も自身に投影し、認識新たに「頂ける」部分は頂き、今後に是非活かしたいと思いました。
実は山本先生の講演を聴くのは2度目で、前回よりも格段に腕を上げられました。(山本先生、生意気言ってすみません)
しっかりとした構成、よどみなく流れる話しぶり、内容もわかり易く、有名選手のエピソードも交え、飽きさせず最後の質疑まで丁寧に答えて頂き、サッカーファンはもちろん、そうでない方にも意義深い講演だと思います。
もちろん人柄も折り紙付きで、典型的なスポーツマンで、明るく笑顔を絶やさず、素敵な紳士です。
懇親会にもお時間の許す限りご参加下さいました。
自信を持ってお薦めできる講師のお一人です。
2016年5月 池谷裕二先生の講演を聴いてきました(企業ご主催)2016/10/17
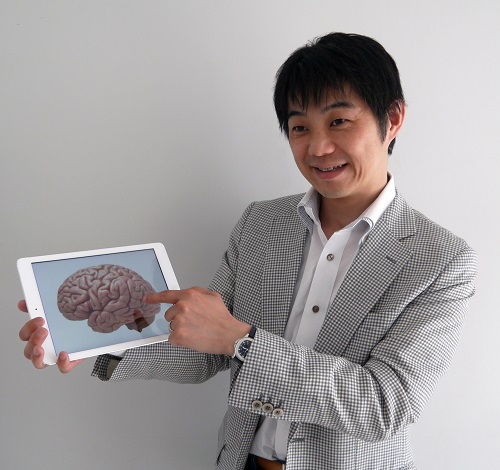
今回は、弊社人気講師!池谷裕二(いけがやゆうじ)先生をご紹介いたします😍
脳科学者・薬学博士であり、 東京大学 薬学部 薬品作用学教室 教授の池谷先生。
私は5月に、弊社お得意様企業の社員向けの講演会にお邪魔し、聴講させて頂きました。
お会いした池谷先生は、ウィットに富んだ会話がお上手なとても気さくな方で(゚∀゚)❤
ご講演の内容はと言いますと、「やる気」「記憶」「遺伝子」のお話。
管理職の方の興味はもちろんのこと、途中途中に目の錯覚のスライドを挟み、
飽きの来ないご講演に、若手社員の方の掴みもバッチリでした👍
私には、特に「遺伝子」のお話が面白く😊
運動で痩せるか、食事で痩せるか、人それぞれ遺伝子で決まっているそうで。
関係ない方を一生懸命やっても、無駄骨だそうです(;_;)どっちなのでしょうか・・❔
最近は日本でも遺伝子検査ができるそうで、先日池谷先生にメールで伺ってみたところ、
「技術も情報も発達している真っ最中なので、もう少し待つと、より良い情報が得られますよ」と、
とても親切にお答えいただきました(;_;)💛遺伝子は一生変わらないので、焦って調べるのはやめにします!笑
私担当の案件で、先週2回ご講演を行って頂きましたが、どちらも大好評!!!
間違いなし\(^o^)/一度聴講して頂ければ、わかります(・ω・)ノ✨✨
ちなみに!ご講演後は、ご自宅🏠でお子様の面倒を見ると!優しいお父様の一面も💝
皆様からのお問い合わせ・ご依頼をお待ちしております~☎📧
(文・スタッフY)
2016年9月 宮家邦彦先生の講演を聴いてきました2016/10/11

神奈川県内で弊社お得意様ご主催の講演会で宮家邦彦(みやけくにひこ)先生の「地政学と日本の大戦略」と題しての講演を聴いてきました。
当日は台風接近に伴い暴風雨という予報で、電車の遅延など交通機関への影響が心配されましたが、ほとんど影響無く、宮家先生もテレビ朝日の「グッドモーニング」出演後、直接ハイヤーにてお入り頂けましたので、思いのほか早く到着されました。
おしゃれなハットにサングラスといういでたちで、背も高くとてもダンディな印象で、物腰も柔らかく、いかにも紳士で優しい先生です。
先生は横浜三ツ沢のご出身。
外務省ではアラビア専門(アラビア語)だったそうです。
今年に入り「地政学リスク(地政学的脆弱性)」という聞き慣れない言葉が今年何度か新聞に関連記事が出た。
ロシアがなぜクリミアへ侵攻したか? 経済的利益を超える地政学的利益が欲しかったから。
(地政学的脆弱性の例)
・イラク ティクリートは肥沃な真っ平な土地で自然の要塞が無い。 北からトルコ、東からペルシャ、西からギリシャ・ローマ、南からベドウィン。イラク戦争後2011にオバマが米軍を撤退させたことでイラクに「力の真空」地域ができてしまった。
・ロシア 北からは無いが東からフン族・モンゴル・中国など、南からムスリム、西からはヒトラーやナポレオン。 自然の要塞は無いがロシア人は敵と戦った。
・南シナ海(フィリピン) 1991/4ピナツボ火山爆発。 1991/11米軍基地(クラークとスービック)返還。 1992/2中国が領海法制定。 基地の返還で南シナ海に「力の真空」が生まれた。
2014に中国船にベトナム船が水を掛け、中国もそれに応酬、これが本当の「水掛け論」と笑いを取られた。(ちょっと驚きましたが外交官はユーモアが無ければいけないのだなと納得)
複数の重大クライシスが起きた場合、米はアジアではなく中東へ行く。
どうするか?
英国の地図を逆さまにすると日本とそっくりになる。
「島国同盟」のすすめ 。
日米同盟に加えオーストラリア、シンガポール、フィリピン、インドネシアと組み、大陸と健全な距離を保ちつつシーレーンを維持する。
今日本が中国に求むべきこと ①東アジア伝統文化と西洋文明の融合 ②巨大帝国ではなく、国民国家の志向 ③力による現状変更を止め国際社会への関与 そのために日本が行うべきこと。
「伝統」を守るには「変化」が必要。 「普遍的価値」で「保守」を「進化」させれば日本は生き延びる。 伝統的文化・価値と普遍性・合理性・国際性との融合こそが東アジアにおける日本の存在価値、と括られ、いくつか質問を受け時間一杯丁寧にお答え下さいました。
日本国とその子孫たちのために我々大人が今何をしなければならないのか、ということを私のような凡人には思いも付かない視点からわかり易く明確に提示され、内容の濃い視野が広がる素晴らしい講演でした。
2016年5月 山本一力先生の講演を聴いてきました2016/08/30

川口で長年の弊社お得意様ご主催の講演会で山本一力(やまもといちりき)先生の「生き方雑記帳2016」と題しての講演を聴いてきました。
川口と言えば鋳物の街、そしてそれを踏まえた講演の冒頭の入り方は絶妙。
上京する直前の中学3年の頃だったと思うが、日活の映画で見た「キューポラのある街」ってどんな所なんだろうと思っていた。
当時日本中がこれから新しい国になるんだといって本当に頑張っていた。
高知も似たような街の雰囲気だった。
子供も大人も前に進むんだと思っていた時代だった。
そしてあの時代に育った人間は「人は一人じゃ生きてないんだ」ということを社会全体がしっかりと教えてくれた。
小学生の頃、やってはいけないこと、しなきゃいけないことを大事に大人が教えてくれた。
母しか居なくて自分と妹が母の細い稼ぎで市営住宅に暮らしていた。
名前は市営住宅だがバラックの長屋のようなもの。
でも皆同じようなものだったので負い目でも何でもなかった。
大人は朝起きてからずっと子供を気にしていた。
子供も安心して大人を頼ることができたし、信用することもできた。
今の社会は知らない人とは口をきいてはいけないという教育の流れになっていると聞く。
違うだろ!と思う。
これを当たり前にしていくと後に続いてくる子供たちは人を信用できないという社会で生きていくことになってしまう。
もう既に始まっている。
「弁え」はお互いが持つこと。
社会から、先生から教わった。
給食が一番のご馳走だった。
これも人が力を貸してくれたからこそ。
人が人を信用して生きていけた時代に他ならなかった。
母から念仏のようにいつもいつも「足るを知れ」と言われた。
生きていられるということがありがたいことなんだと。
そうして生きて行けば人を羨むことは無い。
時代がどう変わっていこうが変わらないものはきっとある。
親が子供に残せるものは「志」しかない。
美田でもお金でもない。
そしてこれは親でなければ子に残してやれないもの。
困った時に杖となる言葉、「負わなければいけない責任には法的な責任と道義的な責任の二つがある。間違っても道義的な責任を法的な責任で押し潰すな」と言われた。
一軒の家というものを考えた時に男が果たせる役と女が果たせる役は全く別物だと思っている。
男ができることはほんの少ししかない。
わかり易く言うと外で稼いできたもの全てをカミさんに預けて家庭を守ってもらう。
その役目においては親父。
もう一つ、家の柱となって家の憲法を家族に身をもって知らしめる。
この二つ以外の役目はカミさん。
従って一家の大黒柱はカミさんだと何の疑問も持たずにそう思っている。
男女同権、それはそれで良いと思う。
しかし断じて同質ではない。
女性でなければできないことは山ほどある。
同質であろうと思うことが無理がある。
母親の子を案じ続ける本能あるが故に子供は育っていくと思う。
ご自身の現在置かれている状況を赤裸々に語られ、折り合いが悪かった義母を親愛の情を込め実母のように「お袋」と呼び、義弟たちの環境を想い、ご自身のご家族が膝を患い歩けなくなるかもしれない「お袋」と一緒に暮らすことを決め、暮らし始めて色んなことが良い方向に変わっていき、その結果「天ぷらばあちゃん」が完全な家族になり、皆にとって大変良かったと話された。
いみじくも仰った「案ずるより産むが易し」。
これから日本で起こり得る家族の問題の理想的な解決方法の一つを提示されたのではないかと思った。
年代的に亭主関白の典型かと思いきや、全くそうではなく考え方が柔軟で女性、母の凄さを認め称賛し、男は絶対に勝てないと言い切る潔さ。
「足るを知ると同時に、知らない所で人が何かしてくれているということを弁えることが大切」と講演を締められた。
日本人とは、親とは、父とは、母とは、弁えるとは、足るを知るとは、痛み分けとは、など多くの不変で私たち日本人の誇りに通じる素晴らしいものを決して押しつけることなく自然に再認識させてもらえた素晴らしい講演でした。
低音で良く通る聴き易い声質、目を瞑ると情景が浮かぶ作家らしい秀逸な表現に包まれ、大変心地良く自然と心に響き染み入ってくるまさに「一力ワールド」です。
おしどり夫婦を絵に描いたようなご夫妻で、いつも通りご一緒に会場入りされ、奥様が甲斐甲斐しく先生の身の回りのお世話をされ、主催者の皆さん、そして私ごときにまでも大変気遣って下さいました。
山本先生は控室で講演直前に主催者の方々へ「どんなことでも講演の中で話して欲しいことがあれば仰って下さい」と言われ、いくつかリクエストを頂き、それを自然な形で、しかも即興で講演の中に取り入れられお話しされていました。
テーマが「雑記帳」とはいえ構成力はもちろん、その知識の広さのみならず深さもあり、直木賞作家の凄さを痛感しました。
2016年5月 谷田昭吾先生の講演を聴いてきました2016/08/01
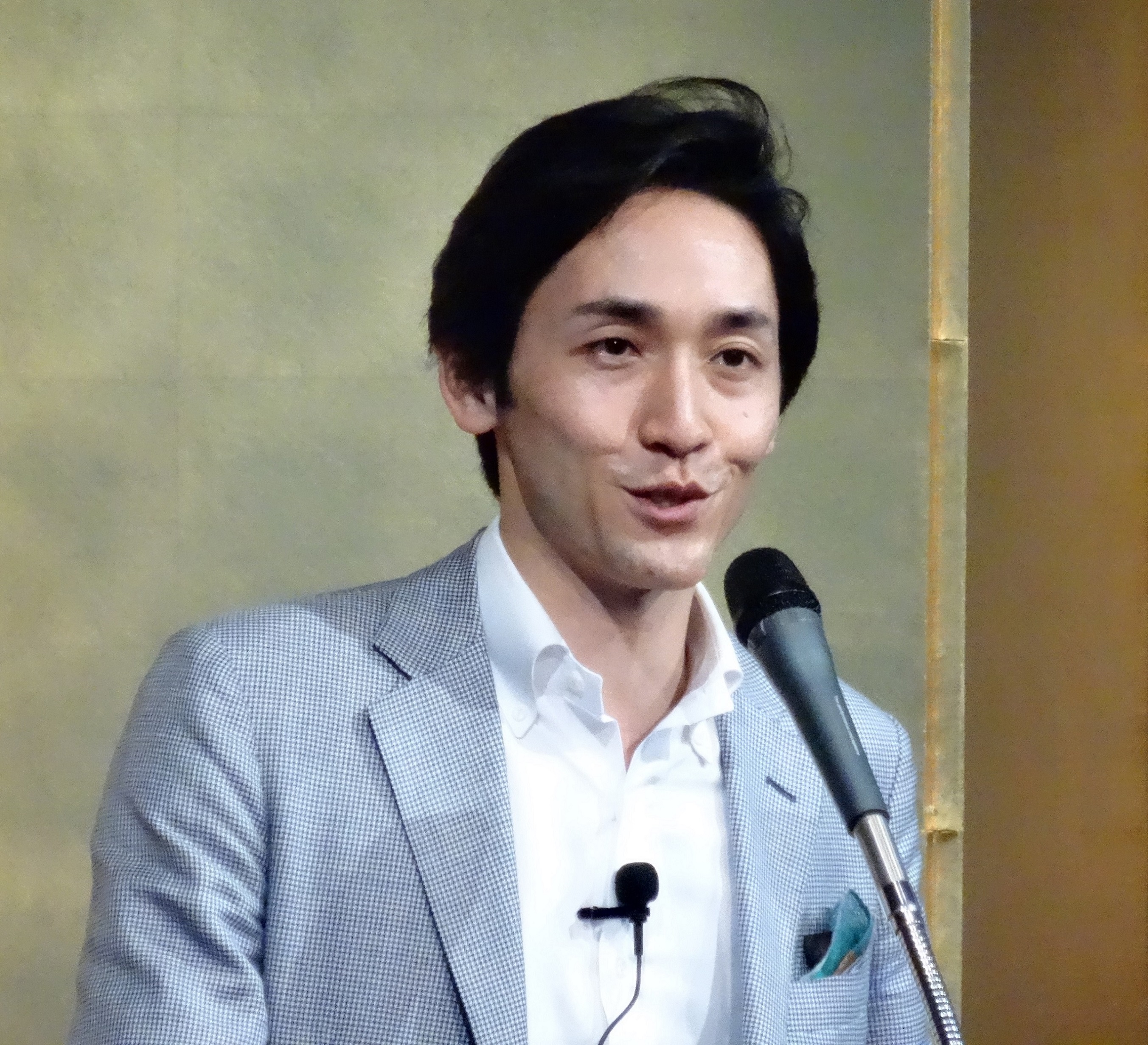
都内で弊社お得意様ご主催の講演会で谷田昭吾(たにだしょうご)先生の「タニタの成功法則 ~タニタを世界No.1へ導いた“経営の秘訣”とは~」と題しての講演を聴いてきました。
まずは自己紹介。
「たにだ」となぜ濁るか?
豊田(とよだ)さんのトヨタが濁らず、同様にタニタにすると同じ八画になり末広がりにもなるから、あるいは左右のバランスを考えて濁点を取ったのではなど諸説ある。
「昭吾」は “吾”の五と口をゼロに見立て昭和50年生まれだからと創業者の祖父が名付けてくれた。
実はこの祖父が体重計を「ヘルスメーター」と命名した。
二代目は父。
講師と現タニタの関係は、3歳上の兄が三代目社長でともに筆頭株主。
①赤字からの脱出、②体脂肪計を創る、③社員食堂の誕生の3つの柱からなる講演。
①赤字からの脱出
創業はもっと古いが72年前の1944年に祖父が設立し、欧米のライフスタイルが日本にも浸透するだろうということで、当時はライターやシガレットケースの製造が中心で、OEMでトースターとごくわずかなシェアでしかなかったヘルスメーターの3本柱だった。
1983年に父大輔氏が社長を継いでから4期連続赤字で累損2億円、タニタは危機的な状態となりライター事業から撤退。
撤退するまでに、まず事業部制にして部門ごとの採算を透明化し赤字部門をあぶりだした。
次に一番辛い時期に「世界一」を目指すという大きな夢を掲げ、「目標設定」をした。
具体的に達成時期の目標設定はしなかったが「口に出した」。
これが一番大きかった。
そして最後に「体重計」から「体重」という事業領域へシフトした。
体重計メーカーから「体重とは何か?」を考えどのようにして人々が健康になるかをビジネスにしようと考えた。
ベースになった考え方は二代目の留学先でのアメリカで体験したことにある。
美術品が好きだったこともあり個人所有の美術館も多く巡り、オーナーがどうやって財を成したかを必ず訊いた。
そして船会社、鉄道会社などで成功した人たちが誰一人として船⇒鉄道⇒自動車⇒飛行機へと時代の変遷に伴いシフトし成功し続けている人がいなかったが、船だけ、鉄道だけと捉えるのではなく、「物流」と捉えていたら上手くシフトし成功し続けていたのではないか、だとしたら自社に照らしてみて何が大切なのかを考えた時に、「体重計」ではなく体重を基に健康を提案する事業へシフトすることこそが一番ではないかと、「体重計」から「体脂肪計」(今でこそ当たり前のように皆が口にしているが「体脂肪」は実はタニタが作った言葉)へと繋がっていった。
そして1990年にタニタ本社に「体重とは何か?」を知るべく「ベストウェイトセンター」(フィットネスクラブ)を作り、大赤字だったが2年後に業務用体脂肪計が誕生、当時50万円くらいした。
そして1994年に家庭用を4万5千円くらいで発売し、大きな夢を掲げて14年後の1997年にヘルスメーターのカテゴリで売上世界一を達成した。
②体脂肪計を創る
イノベーション理論に基づく成功するための5つの行動習慣。
1)つながる(=ネットワークする)
「ベストウェイトセンター」構想で肥満専門医とつながった。
2)質問する
肥満専門医に「肥満は体重ではなく脂肪」と言われ「脂肪って何ですか?どうやれば測れるのですか?」とわからないことを素直に訊いた。
3)関連付け
ヘルスメーターに脂肪計がくっ付けられないか?⇒くっ付けた・・・組み合わせが大事
自社の得意なものに何を関連付ければ良いかを考えた。
4)実験する
社長のアイデアをキャリアのある開発者に伝えた⇒「できるわけない」⇒先入観や固定観念の無い新入社員に任せてみた⇒2年で目途が立ち商品化された
専門家に無理と判断されても無理強いせず、仕方なく妥協し新入社員に任せたら「できるかもしれない」、「達成したい」と思ってくれ実験し、変革へとつながり商品化できた。
5)観察する
顧客の一番大きな不満から改善していく。
タニタの場合は分かれていた人が乗る部分と大き過ぎる表示部の不満をなくすため小さくしていき、現在はコードレス一体成形型へ。
タニタの製品を全て社長が使っていたので谷田家の風呂場には常に体重計が5~6台あった。
それが当たり前だと思っていたら友人の家に行くと1台しかなく、自分の家が異常なんだと知り驚いた。
③社員食堂の誕生
社員食堂を立ち上げた管理栄養士の方は、現在73歳(2016年現在)。
いくつもある指導法の中から1つだけ自分の生活習慣に取り入れ易い方法を選ばせ、意識して続けさせるというやり方をしている。
この管理栄養士の方も所属していたのが前出の赤字垂れ流しの「ベストウェイトセンター」。
1990年から9年続いたが交通の便の良い所に安いフィットネスクラブがたくさんでき、入会金30万円で高かったので集客できず役目は終わったということで閉鎖することに。
その時に過去、4期連続赤字最後の年黒字転換させるために、板橋から秋田へ工場移転する時に従業員が子供の学校のことなどもあり縁の無い秋田行きを断り、泣く泣くリストラをしなければならなくなった暗い失敗の過去があったため、一緒に仕事をしたい、絶対にリストラはしたくないという強い思いから働いていた管理栄養士の方々にそのままベストウェイトセンターを社員食堂に変え、移ってもらった。
そして2010年、1999年から11年かかって社員食堂のレシピ本が発刊され、タニタ食堂へとつながっていく。
社員の健康のためにできることをということで始めた事業が継続することで蓄積され、独自性に磨きがかかり注目され、現在の成功へと自然に導かれていった。
講演の最後の部分で創業者である祖父が「経営とは人間管理」(顧客も従業員も株主も人間)と書いた色紙を二代目に贈ったというエピソードを披露。
甘いマスクに物腰の柔らかな語り口、見るからに生まれも育ちも良さそうなお坊ちゃんで一見するとひ弱に見えるかもしれないが、一本筋の通ったしっかりした考えをお持ちで芯の強さを感じさせてくれるこれから期待の講師です。
今回も3つのパートを30分ずつ計ったかのような見事な時間配分。
それぞれ内容も濃く、タニタの自慢話ではない失敗も含めながら様々な困難を乗り越え現在に至る道程を熱く話された素晴らしい講演でした。
2016年5月 真田徹先生の講演を聴いてきました2016/07/22
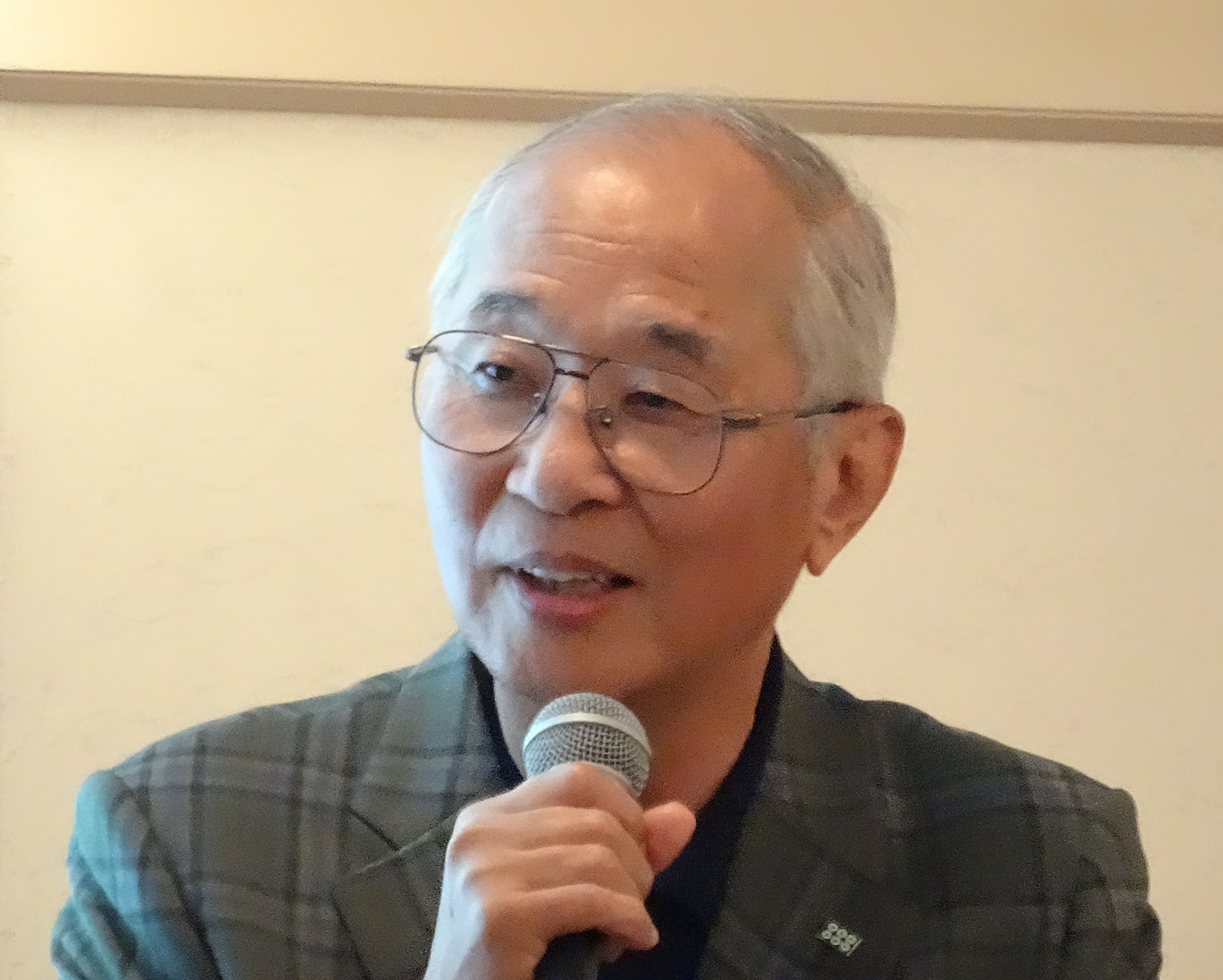
都内ホテルで長年のお客様ご主催の講演会で真田徹(さなだとおる)先生の「真田幸村 虚像と実像」と題しての講演を聴いてきました。
真田先生は真田幸村の二男(大八)の家系(仙台真田家)。
京都に疎開、伊達氏に拾われ奥州に下り何となく今まで家系が保ったという家。
長男は幸昌、ほとんど実績が無かったので10分もあれば話が終わってしまう。
しかしなぜか名前だけが残った。
今年のNHK大河ドラマ「真田丸」。
上田市の町興しでNHKに5~6年前から県を挙げて働き掛けを始め、県知事、各市町、町村長まで引き連れ「是非お願いします」と年に3回ぐらいNHK通い。
当初NHKはけんもほろろだった。
木で鼻をくくったように「その内いつか実現するでしょう」と言われ続けた。
そうこうしている内に急に「決まりました」と連絡が来た。
私自身はあまりやって欲しくなかったが行政は喜んでいて「私の力で」なんてみんなが言っている。
信州真田家は放牧で生計を立てていた。
馬はすぐ現金になったから。
山伏を調べるとほとんどが真田忍者だった。
ルーツである幸隆からの子孫たちの話。
上杉謙信、武田信玄との関わり。
魑魅魍魎、権謀術数の世の中だった戦国時代模様。
大河ドラマのタイトル「真田丸」とは?
大坂冬の陣の時の砦。
「真田丸」に引き付けて敵を叩く作戦。
簡単に説明すると狭い所で待ち構え、敵の大軍が入って来た所で鉄砲隊が一斉攻撃し、退却しようとしても後ろからどんどん来て退けず被害を拡大させる戦法。
徳川方の損害の7割が「真田丸」の戦いによってもたらされたと言われている。
実は真田はこの戦法を長野時代から何度も成功させていた。
大河ドラマの補足説明あり、独自の展開予想もあり。
手紙も古文書にも何も残っていないので証拠は無いが伊達政宗と真田幸村との間にもし幸村が家康の首を取れば天下は取れないが幕閣は押えられるだろうからその暁には厚遇するし、万一失敗しても幸村亡き後子女たちの面倒は看るという密約があったらしい。
おそらく事実だったと思う。
なぜなら正宗は本当に幸村の子女を4人も5人も引き取り仙台へ連れて帰り城まで与え仙台真田家として残しちゃんと面倒を看たから。
手紙に書いてあることは必ずしも事実ではなく、後世に残す為に意図的に書いたものが数多くある。
戦国武将たちの出自が天皇家に繋がるなどの嘘も当たり前だった。
そして嘘をつかれた方も「そうかそうか」みたいなことが往々にしてあった。
などなど。
幸村ファンはもちろん戦国時代や歴史に興味をお持ちの方はかなりマニアックではありますが十分楽しんで頂けると思います。
ヘビースモーカーのちょっとお茶目な先生です。

お問い合わせ・ご相談は
- [受付]9:00~18:00
[定休]土日祝 - 03-5386-3341
日本綜合経営協会は、全国47都道府県を対象に講演依頼に基づく講師派遣や、企画提案などを行なっております。
主催者の開催目的に合わせた最適なご提案から、手続き運営サポートまで。業歴50年、経験豊かな当社スタッフにトータルでおまかせください。